言葉によるコミュニケーション
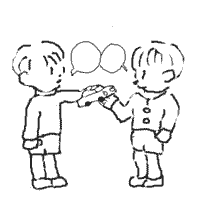
今回からは、「問題解決能力」のお話です。
私たち大人が、子どもたちを育てていく上で、最終的に身に付けさせたいのが、この能力だといっても過言ではないかもしれません。「問題解決能力」には、「言葉によるコミュニケーション」「解決の方法」「自己コントロール」という、3つの側面があると考えます。
子ども同士の遊びにトラブルはつきものです。まして、「ごっこ遊び」は、その設定や配役、ルールまで、子供同士で作り上げていく遊びですから、その過程では、当然、数々のトラブルが起こってきます。そのトラブルを通して、周囲の助けを借りながら乗り越えていく過程で3つの力が身についていくのです。
まず、「言葉によるコミュニケーション」です。
3歳位になると、日常会話は、子ども同士でも、かなり成り立つようになってきます。しかし、いざという時になると、言葉にならないというのもよくあることです。
友達の持っているおもちゃが欲しくて、「貸して」と言えず、無理やり取ってしまう子・「いやだ」と言えず、黙り込んでしまう子・自分の思い通りになるまで、泣きわめく子・・・・・等々、珍しい姿ではありません。
そんな時、大人のちょっとした手助けがあると、子どもは、その場面に必要な言葉を身に付けていきます。
「『貸して』って言おうね」
「いやな時は『いやだ』って言っていいんだよ」
「悪いことしちゃったから『ごめんね』って言おう」
その他にも、『後で貸してね』『ちょっと待っててね』などの言葉もあります。
初めは、うまく「言葉」で解決できなかった子どもたちも、
「たたいたら、泣かれちゃった。でも、『ごめんね』って言ったら、仲良くなれた」とか、
「『いやだ、いやだー』って言ってたら、だーれもいなくなっちゃった。でも、怒らないでお話したら、ずっと一緒に遊べて楽しかった」
といった経験を繰り返し、友達と楽しく遊ぶのには、「言葉」で伝えるのが大切だと気付いていきます。
そして、5〜6歳になった子どもたちは、もっと複雑な気持ちや、事の成り行きを言葉で表現することができるようになっていきます。
「私、本当は、赤ちゃん役がよかったんだよ。でも、毎日、赤ちゃんばっかりでずるいって、○○ちゃんが言うから、今日はやめたんだよ。」
「さきに△△君が使ってたボールなんだから、返してあげなよ。」
など、ただ泣くだけでは、ただ奪ってしまうだけでは、解決しないことを、子どもたちは、ちゃんと学んでいるのです。
次回は、「問題解決能力」の中の「解決の方法」について、お話します。
(2005/3/15)
